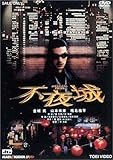果てしなき旅〈上〉 (岩波文庫)/岩波書店
¥693
Amazon.co.jp
果てしなき旅〈下〉 (岩波文庫)/岩波書店
¥693
Amazon.co.jp
E.M.フォースター(高橋和久訳)『果てしなき旅』(上下、岩波文庫)を読みました。
E.M.フォースターは、世界の文学の中でもとりわけ印象に残る作品を残した素晴らしい作家です。しかしながら、同時に話題になることが少ない作家でもあるんですね。それは一体何故なのでしょうか。
文学的な評価は置いておいて、読書好きの間でフォースターが話題にならないのは、間違いなくイギリス文学に他に有名な作家、たとえばジェイン・オースティンやサマセット・モームがいるからでしょう。
フォースターは価値観があわない恋愛をテーマに小説を書くことが多かったのですが、それはまさにオースティンのテーマと重なります。また一方で、半自伝的小説というテーマではモームと重なるのです。
つまり、フォースターの『ハワーズ・エンド』よりもオースティンの『高慢と偏見』、フォースターの『果てしなき旅』よりもモームの『人間の絆』の方が人気があるのでそちらが話題になるということ。
人間の絆〈上〉 (岩波文庫)/岩波書店
¥987
Amazon.co.jp
ぼく自身も、率直に言えばフォースターよりもオースティンやモームの方が好きです。理由ははっきりしていて、オースティンはユーモアやウィットに富んでいますし、モームは物語的で、より面白いから。
つまり、残念ながらフォースターはオースティンに比べるとウィットに乏しく、モームと比べると物語性に欠ける作家と言えるでしょう。
ですが、フォースターの面白さというのはまさにそうした地味で、とことんリアルな人生が描かれている所にあります。テーマの深さという点ではオースティンやモームをも陵駕している感じがあるのです。
物語的な面白さはともかく、写実的な作風なだけに、テーマとして考えさせられることが多く、読者がもう一度、自分の人生について考えてみたくなるくらい心を動かされる作家がフォースターなのでした。
決して派手さはないですし、人生の苦みを描く作品が多いので読んでいてあまり楽しい気分にはなりませんが、小説を読む喜びを感じさせてくれる作家なので、ぜひ作品を手に取ってもらいたいと思います。
さて、今回紹介する『果てしなき旅』は、理想と現実に苦しむ作家志望の青年の姿を描いた半自伝的作品。六作あるフォースターの長編小説の中でぼくが最も好きな小説で、何年かに一回必ず読み返します。
芸術肌の主人公リッキーが、結婚や仕事を通して徐々に現実に打ちのめされていくことに引き込まれる小説ですが、何よりもリッキーの親友のアンセルが印象的。ぼくはその変人アンセルが好きなんですよ。
好きというと少し違いますね。アンセルは偏屈者で世の中を斜めに見ている、哲学者気取りのやつなんです。自分が存在していると認識すればそれは存在し、認識しなければ存在していないとか言うタイプ。
実に扱いづらい、まさに変人ですが、その歪んだ性格や考え方がぼくは分からないでもないだけに、妙に惹かれる部分があるんですね。純粋なリッキーと対照的なアンセルにも、ぜひ注目してみてください。
芸術的な理想を追い求めれば生活は遠のき、生活を安定させようとすれば、芸術からは遠ざかってしまうもの。そうしたジレンマを抱えた小説家の半自伝的作品は傑作が多いですが、中でもおすすめの作品。
作品のあらすじ
こんな書き出しで始まります。
「その牛はそこに存在する。」マッチに火をつけ、カーペットの上に差しだしながらアンセルが言った。誰も口を開かない。彼はそのまま、マッチが落ちるのを待ってから、ふたたび言った、「そこに存在するのだ、その牛が。そこに、いま。」
「まだ証明できてないじゃないか」と別の声。
「自分に対してはもう証明したのさ。」
「ぼくは牛はいないと自分に証明したぞ」とその声。「その牛はそこに存在してはいない。」アンセルは顔を顰めて、もう一本マッチを擦った。
「ぼくにとって牛はそこに存在するのだ」彼は言い放った。「君にとって存在しようがしまいが構わない。ぼくがケンブリッジにいても、アイスランドにいても、あるいは死んでいようと、その牛はまちがいなくそこに存在する。」(上、7~8ページ)
ケンブリッジ大学の学寮では、みんなが盛んに哲学談義を交わしていました。中心になっているのは、片足が悪いこともあり、ずっと孤独に生きてきたリッキーにとって、初めて出来た親友アンセルでした。
そこへ美しい女性がやって来ます。みんなは色めき立ちますが、アンセルだけは一人無反応。その女性はリッキーの知り合いのアグネスで、兄のハーバートと一緒にリッキーのことを訪ねて来たのでした。
リッキーに紹介されてアグネスは手を差し出しますが、アンセルはマッチを持ったまま微動だにしません。アグネスは気まずい思いをして、リッキーは後からアンセルの態度を謝ることになったのでした。
リッキー、アグネス、ハーバートは食事を取りますが、その席でアグネスから婚約のお祝いを言っていないことを指摘されたリッキーは戸惑います。お祝いの言葉どころか今婚約を始めて知ったのですから。
アグネスは、かつてリッキーをいじめていたこともあるジェラルドと結婚が決まっているのでした。幸せいっぱいのアグネスでしたが、ジェラルドはラグビーの試合で起こった事故で死んでしまったのです。
事故の直後リッキーは絶望しているアグネスの元に駆けつけました。
彼は彼女のとなりにひざまずいた。彼女は言った、「一人にしてくれないかしら。」
「もちろん、すぐに行くとも、アグネス。だけどまず君が心に留めているってことを確認しなくてはね。」
彼女ははっと息を飲んだ。彼女の目は足跡を追った。外へと向かっていく、確固とした、二度と戻ってこない足跡を。
リッキーは喘ぎながら言った。「今度のことは君の人生で起こりうる最悪の出来事なのだ、だから君はそれを心に留めなくてはならない、忘れてはいけないんだ。みんながやってきて言うだろう、『じっと耐えろ、時間が忘れさせてくれる』と。でもそれは違う。みんな間違っているんだ。心に留めておくんだ。」
打ちひしがれた気持ちのなかで彼女は、この若者がみんなの考えている以上の人間であることを悟った。(上、101ページ)
やがてリッキーとアグネスが婚約したことを知って、アンセルは怒ります。「わたしには分かりました」ではなく、「わたしたちには分かりました」と言ったアグネスをアンセルは気に入らなかったのです。
アグネスはリッキーを堕落させ、人生をめちゃくちゃにしてしまうと思ったアンセルは、何度も二人の結婚をやめさせようとしますが、アグネスを愛しているリッキーの耳にその言葉は聞こえないのでした。
リッキーは既に両親をともに亡くしているので、キャドヴァーで暮らしている伯母の所へ挨拶に行きます。父の姉にあたる人物。屋敷には伯母が面倒を見ている粗野な若者、スティーヴンの姿がありました。
そして帰り際に、リッキーは衝撃的なことを聞かされたのです。
スティーヴンはリッキーの片親違いの弟なのだと。リッキーは動揺し、冗談だと思ってそれを笑い飛ばそうとしますが、父親がロンドンに部屋を持っていたことを思い出し、体中に戦慄が走ったのでした。
小説家としてやっていきたいと思うリッキーでしたが、いつまでも芽が出ません。アグネスはひとまず教師になることをすすめます。長い休暇があるので、その間に好きな原稿を書くことができるだろうと。
「でもぼくの書いたものなど、だれも読みはしないさ。」そしてリッキーは『ホルボーン』誌の編集者との面談の様子を彼女に話した。
アグネスはすっかり真顔になった。心の底ではついぞ彼の短編を評価したことがなかったのだが、いまや、目利きの人々が自分と同意見ではないか。リッキーは、いや彼に限らず、ギリシャの神々は生きているとか、若い令嬢が木に変身したらしいといった荒唐無稽なことを書いて、生計を立てていかれるはずがない。活気にあふれた社交界の物語で、そこに熱情と悲哀が十分盛り込まれていたら、話は違っただろうし、編集者も説得力があると思ったかもしれない
「でも彼はいったい、何が言いたいのかな?」リッキーが話していた。「人生という言葉で何を言いたいのだろう?」
(下、16ページ)
イーストン校の教師になり、アグネスと結婚したリッキーでしたが、学校では派閥争いに巻き込まれて疲弊し、アグネスとの心の距離は縮まっていかぬまま。小説の方はまったく書けなくなってしまいます。
遊びに来ないかとアンセルに手紙を書きますが、それが「何とも哀れっぽい――牢獄からの悲鳴」(下、57ページ)のように不幸を匂わせるもので、自分でも驚きました。そして招待を拒否したアンセル。
アグネスは遺産を手に入れるため、リッキーの伯母との関係を深める努力をし始め、やがて、自分がリッキーとは兄弟であるという真相を知ったスティーヴンははるばるリッキーを訪ねて来たのですが……。
はたして、リッキーとスティーヴンの関係はどう変化するのか? そして、リッキーは作家としての成功を手に出来るのか!?
とまあそんなお話です。リッキーは片足をひきずって歩くこともありますし、性格もやさしいので、簡単に言えばいじめられっこでした。なので、一人で物語を考えることが何よりの楽しみだったんですね。
しかしその才能はいつまでも経っても認められず、やりたくないこともしなければならない教師の仕事や結婚にまつわる問題で、リッキーの人生はどんどん窮屈で苦しいものになっていってしまうのでした。
リッキーとアグネスの結婚は熱烈な恋愛から始まったものではなかったですよね。リッキーの想いは美しいものに対する崇拝のようでしたし、アグネスの想いは信頼出来る相手に対する敬意のような感じで。
そうした結びつきはいくつかの出来事を経て、大きな危機を迎えることとなります。一つ一つの出来事はささいな事柄なだけにとてもリアルで、結婚について、しみじみと考えさせられるものがありました。
まさに人生そのものを描き出したと言うべき長編です。物語に入り込みやすい作品なので、興味を持った方は、ぜひ読んでみてください。
明日もE.M.フォースターで『ハワーズ・エンド』を紹介します。